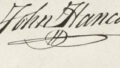カンボジア難民が築いた、アメリカ西海岸の”ドーナツ文化”
ドーナツ文化
今回は、私が暮らすアメリカ西海岸、特に南カリフォルニアを中心に根付いている「ドーナツ文化」についてご紹介します。
こちらでは朝の通勤時間、コーヒー片手にピンク色の箱を抱えて歩く人をよく見かけます。オフィスの休憩室にもその箱が置かれていることが多く、誰もが中身を知っています。開けなくてもわかるーそう、ドーナツです。
箱を見るだけで、ふわっと甘い香りが頭に浮かび、口の中によだれが…もう完全に条件反射。まさに「パブロフの犬」状態です。
仕掛け人
この”ピンクの箱文化”の仕掛け人は、1970年代にカンボジアから難民としてアメリカにやってきた一人の男性、テッド・ノイ(通称 Uncle Ted)さん。
彼はポル・ポト政権から逃れ、英語も話せず、学歴も職歴もないところから、ドーナツショップで働き始め、やがて自分の店を持つまでになります。
そして成功を収めた後は、同じような境遇のカンボジア難民たちにビジネスモデルを伝え、多くの仲間たちをドーナツ業界に導いていきました。
その結果、今ではロサンゼルスでは約7,000人に1軒のドーナツショップがあるといわれ(全米平均は3万人に1軒)、カリフォルニアには約5,000軒の個人経営の店があり、そのうち約80%がカンボジア系の経営者によるものだそうです。
私が住む町にも、家族経営のドーナツショップがあちこちにあり、24時間営業なんていうお店も珍しくありません。
なぜ”あの箱”がピンクなのか?その理由
理由は3つあります。1つ目は、白い箱がカンボジア系移民のルーツである中華文化では「喪」を連想させる不吉な色だから。2つ目は、ピンクの箱がほかの色よりも印刷コストが安かったこと。そして3つ目は、ピンクが中国文化で縁起のいい「赤」に近く、明るく華やかだから。
こうして、縁起が良くて、コストも抑えられ、印象的なピンク箱がドーナツの定番になったというわけです。
今では私も、あの箱を見るだけで「ドーナツ!」と反応してしまいます。コーヒーがさらにおいしくなる瞬間です。
後日談
ちなみに、Uncle Tedさんのその後の人生も映画のよう。ドーナツビジネスで築いたお店と財産をギャンブルで失い、家族もバラバラになってしまいます。そんな波乱万丈な半生は2020年に「The Donut King」(監督:アリス・グー)というドキュメンタリー映画になりました。
ピンクの箱の中には、実はそんなアメリカンストーリーも詰まっているのです。